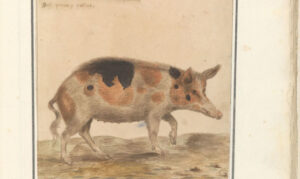参道沿いに並ぶ大きな石6個、大きいもので重さ100キロです。神社の境内にあった石が、なぜか移されていました。かつて、力くらべに使われていた石…。簡単に運ぶこともできず、住民たちは困惑しています。
記者:
「富山県小矢部市棚田の神社の境内です。ここに6個の石が並んでいるんです。最初は、あちらの隅に並んでいましたが、一体誰が、この石を運んだんでしょうか」
神社の参道沿いに並ぶ大きな石、6個…。
以前は手水舎のそばにありましたが、1か月ほど前、近くの住民が参道沿いに移動しているのに気付きました。
しかも、これほどの石を引きずった跡がありません。
地域の歴史について調べていた松井賢三さん。
移動したのを知ったときは、驚きを隠せなかったといいます。
ふる里おやべ再発見推進委員会 松井賢三さん:
「人間にしたって、誰かしらが出したんだろうね。順番に並べたがいちゃ。これがまた本当に、私もびっくりして、ここへ来て…どうしてこういうことに」
■かつて若い衆が力自慢と異性へのアプローチのために…
石の重量は、およそ40キロから100キロ。しかも重い順にきちんと並べられています。そもそも、この石は…。
ふる里おやべ再発見推進委員会 松井賢三さん:
「先人たちは、“盤持ち石”をこうやって持ってきて肩にかけて。それで『わしはこんなに力持ちやぞー!』というかたちで力自慢になり、異性へのアプローチにもなっていた」
「盤持ち石」は明治から大正時代、各地の神社で行われた力くらべで使われていた石です。
力くらべは現在、一部を除きほとんどみられることもなくなりましたが、使われていた石は各地に残っているといいます。
全文はこちら
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/tut/192984