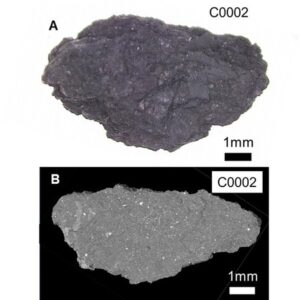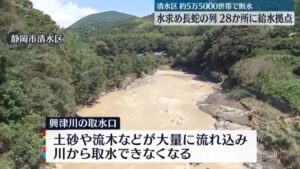冷蔵庫の奥に、キュウリを何日間も眠らせてしまったことはありませんか? 気付いた時にはふにゃっとしなびた状態で、諦めて捨ててしまうなんてことも…。実は、そんなキュウリを簡単に復活させる裏技がある。用意するのは、食品保存袋「ジップロック」と水だけ。「ゴミ箱行きはちょっと待って」<中略>
切って水に浸すだけ!?
「キュウリは9割が水でできているんです。しなびた状態は水分不足になっているだけ」と高橋さん。原理としては、水分を補給してやれば元に戻るという。方法は、
①両端を落として半分に切る。
②ジップロックに水を溜めてキュウリを浸す。
③野菜室で一晩寝かせる。
以上の3ステップ。これだけで味も変わらず、パリッとした食感が戻るという。
全文はこちら
https://news.yahoo.co.jp/articles/db17542c34dee5bd1d08973462c519d129a7998c