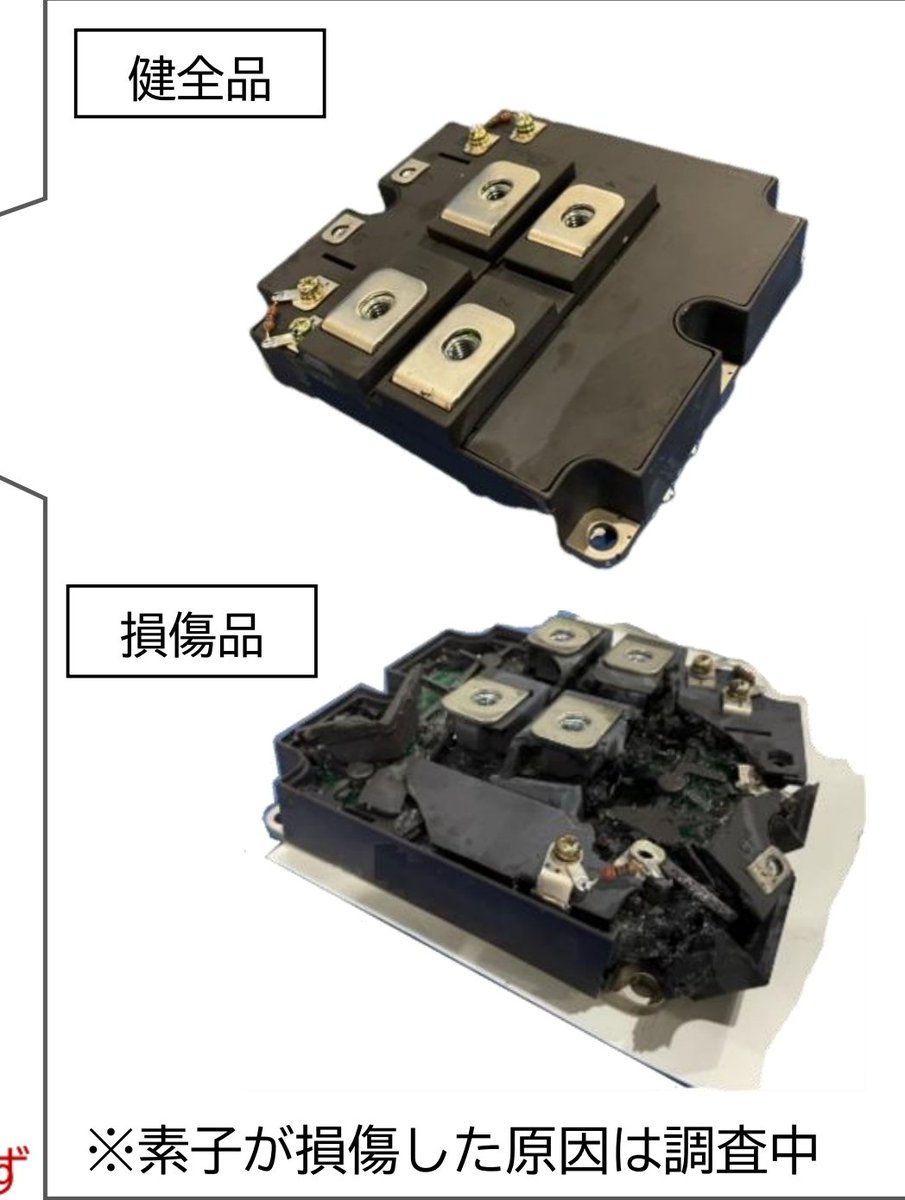ここだけわろた pic.twitter.com/HHvw93snVV
— マソ (@maso_s13) June 26, 2025
警視庁によりますと、カスタムショップの社長・山本伸一容疑者(55)は去年10月、不正な改造パーツをつけたランボルギーニを千葉県の車検場に持ち込み、法律で必要な点検と整備をせずにうその証明書を作り、不正に車検を通させた疑いがもたれています。
この車検場の責任者を務める成田国造容疑者(80)と、山本容疑者の関連会社に勤める川田将大容疑者(32)らも逮捕されました。
JNNは逮捕前、川田容疑者が立ち会い、ランボルギーニが運輸支局で車体の調査を受ける様子を撮影していました。
検査官や捜査員が車体を確認する中、運転席に乗り込む川田容疑者。アクセルを踏み込むと、余りの大きな音に検査官らはとっさに耳をふさぎます。
ランボルギーニは、より大きなエンジン音がするようマフラーが不正に改造され、車体に電飾を施すなど、車検の適合基準を満たしていませんでした。
警視庁によりますと、成田容疑者の車検場は8年ほど前から数百台の不正車検を行っていたとみられていて、山本容疑者は「30万円ほどで不正車検を依頼した」と容疑を認めているということです。
https://www.youtube.com/watch?v=bVck_HwrKDs