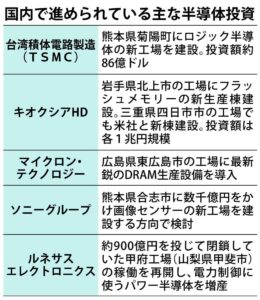トーヨータイヤは、二酸化炭素(CO2)をブタジエンに高い収率で変換する触媒を富山大学と開発し、タイヤの主原料であるブタジエンゴムの合成に成功したと発表した。自動車タイヤの原材料は天然ゴム以外の約4割を占める合成ゴムのうち、石油由来のブタジエン系ゴムが約3割を占める。CO2を石油の代替原料としてタイヤ原料に再利用し、脱炭素化を推進する。2020年代末までに実用化を目指す。
開発したのは、CO2をエタノールに変換する新たな触媒と、エタノールをブタジエンに変換するゼオライト系触媒。最高変換率はCO2からエタノールが40%、エタノールからブタジエンが60%で、技術としてはトップレベルの高さとする。
高価な貴金属を使わない安価な固体触媒により高水準の触媒性能を可能にした。島一郎執行役員技術統括部門中央研究所長兼エンジニアリング本部長は「持続可能なタイヤ原料としてCO2を活用する技術となり、独自性がある」と説明する。
実用化に向け、品質やコストの改良に取り組む。共同開発した富山大の椿範立学術研究部教授は「高単価で市場が大きいタイヤにCO2を活用すれば、触媒技術を有効に生かせられる」としている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/8eaf79fcbe97226ab5544300ec52cca545afb315