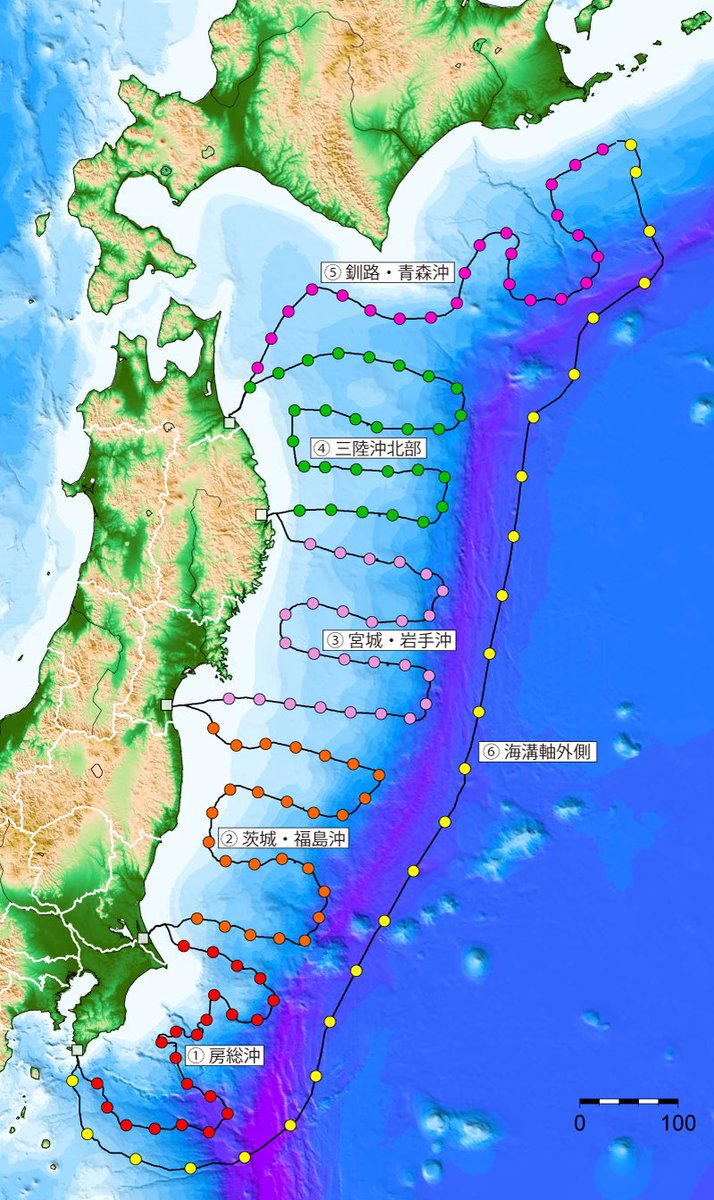【津波】久慈港では1m30cmを観測。
— 名前はまだない (@doshitandaigak1) July 30, 2025
NHKでは久慈港の様子を早送りで解説。 pic.twitter.com/lpUucscmvq
【映像】岩手 久慈港で1m30cmの津波観測
午後1時52分に1m30cmの津波を観測した岩手県の久慈港の映像です。
午後1時から午後2時までの1時間をおよそ400倍で早送りをすると海の潮位が上がったり下がったりしてつながれている船が大きく揺れる様子が確認でき、午後2時には、海面が港の路上とほぼ同じ高さまで上がっている状態となっていました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250730/k10014879421000.html