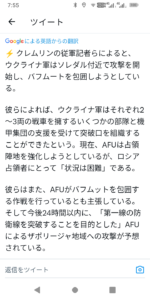ワグネル創設者が暴露…傭兵とロシア軍の対立深まる 「兵器不足」のロシア、69年前の旧式戦車まで動員
ロシア軍とロシア傭兵集団ワグネル・グループがウクライナ侵攻作戦をめぐって対立している中、最大戦闘地域である東部バフムートからロシア正規軍部隊の一部が後退した。このため、バフムート占領の失敗をめぐり双方の対立がさらに大きくなる見通しだ。
ウクライナ地上軍司令官のオレクサンドル・シルスキー将軍は10日(現地時間)、激しい市街戦が繰り広げられているバフムートで、
自国軍が反撃を加え、ロシア軍が2キロほど後退したと明らかにした。ロイター通信などが報じた。
ウクライナの第3独立強襲旅団は別途声明を出し、「ロシアの第72独立自動車化歩兵旅団が、バフムート周辺で500人の戦死者を残したまま脱出したという(ワグネル・グループ創設者の)プリゴジンの発言は事実」だと主張した。
これに先立つ9日、エフゲニー・プリゴジン氏は「ロシア軍が逃走している。第72旅団は今朝、3平方キロの面積の(占領)地域を失わせた。ここで私は約500人の戦士を失った」とし、ロシア軍に対する強い不満を吐露した。
全文はこちら
https://japan.hani.co.kr/arti/international/46717.html