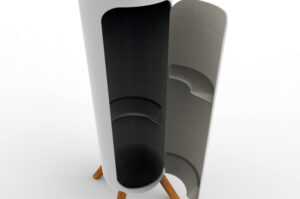Facebookが、URLに埋め込まれるパラメーターのフォーマットを変更したことが明らかになった。一部ブラウザーが実装したパラメーター削除機能への対策とみられる。
これまでFacebookでは、ユーザーを追跡するためのパラメーターを、URLの後半に「?fbclid」という文字列で連結して埋め込んでいたが、これが新たに「pfbid」という文字列に変更されているのが確認された。
先日、Firefoxがこれらパラメーターを自動削除する機能を新バージョンに搭載し、ユーザーからは好評をもって迎えられていたのだが、今回の仕様変更によって機能しなくなる。
また、こうしたパラメーターの多くが「?」でつなげられることを利用し、クリック1つでパラメーターを削除できるブックマークレットも存在したが、「?」を含まない今回の文字列ではこれらも機能しなくなる。
全文はこちら
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/yajiuma/1426324.html