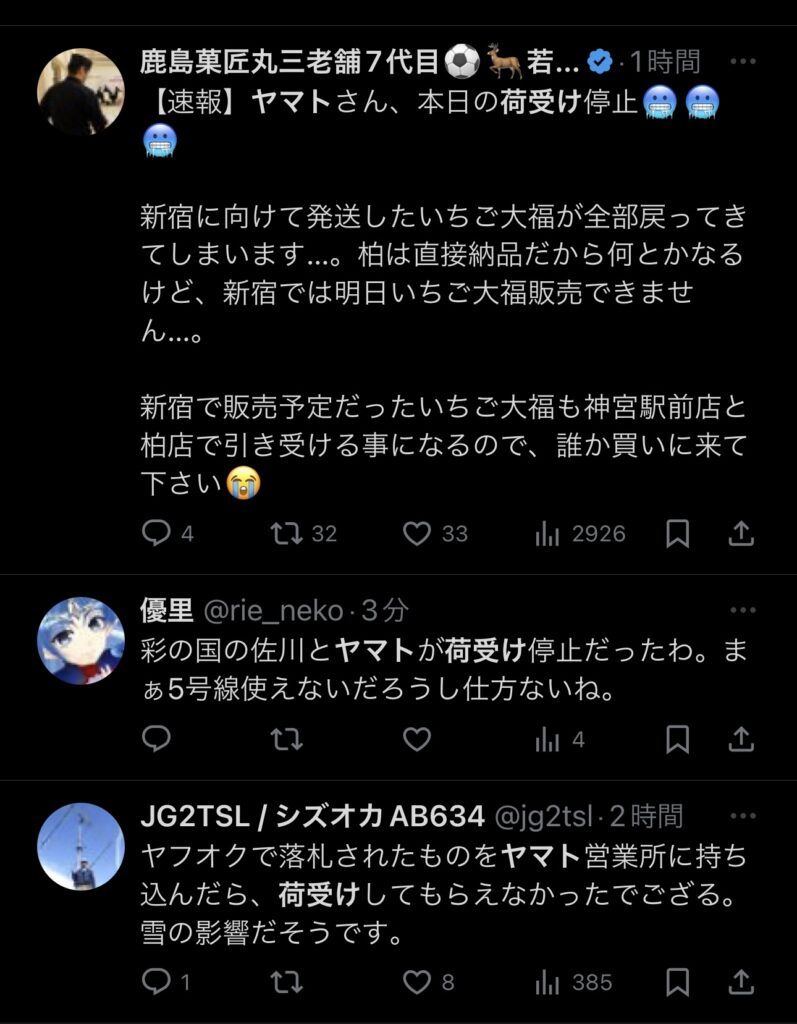札幌で10℃超え55年ぶりの暖かさに街はパニック、ザクザク道路で配送トラックは遠回りを選択、落雪事故で男性搬送、どうなるワカサギ釣り
まるで春の陽気…困ったことも起きています。
13日の札幌市内の気温は10度を超えました。この時期としては実に55年ぶりの記録的な暖かさです。
北海道全体も4月並みの気温に…一気に進む雪どけの影響を、もうひとホリします。
堀内大輝キャスター(札幌市北区 午後2時)
「車が通ると水を飛ばしながら走っていきますね、人も車も注意が必要です」
札幌市北区では雪が緩み水たまりだらけ。そして…
堀内大輝キャスター
「こちらの建物と建物のあいだ雪庇が飛び出していて、しずくがぽたぽた落ちているのわかりますね」
札幌市北区を流れる茨戸川では、氷の上でワカサギ釣りを楽しむ人たちが…
堀内大輝キャスター
「美味しい。ふわっふわ」
客
「きょう暑い。ホッカイロいらない」
表面の雪が溶けている箇所もありますが、この暖かさで、氷が割れてしまう心配はないのでしょうか?
とれた小屋ふじい農場 安斎哲也さん
「上っ面に積もった雪の表面は、溶けてきますので毎日溶けた部分をスノーモービルで踏み固めて雪橋(?雪氷か?)を作って、溶け続けないような対策をとっている」
少しでも長く釣りが楽しめるよう、安全対策に力を入れています。
現場に急行する1台の車…向かった先にいたのは、灯油の配送車です。 ザクザクの路面にはまり、動けなくなっていました。
東区の『ミナミ石油』では、灯油の配送車が埋まってしまった場合、別の部署の社員が”救助”に駆けつけます。
脱出すると、すぐさま灯油の配送に向かいます。
ミナミ石油・配送員・上野恭凪(きょうか)さん
「ここ怖いな…、右行きますね。道も選ばないと、ハマっちゃうところあるので…」
住宅街の細い道は埋まりやすいため、あえて遠回り。
さらに、到着しても気は抜けません。家の裏にあるタンクにたどり着くのは一苦労です。
ミナミ石油・配送員 上野恭凪(きょうか)さん
「(雪が)軟らかいので濡れるのは覚悟で。上(の雪)は注意して下に立たないようにしている」
気温が7度を超えた留萌市では、店舗の屋根の下で、高齢男性が倒れているのが発見されました。
男性は、頭にけがをしていて病院に運ばれました。
屋根の雪下ろし中に、転落した可能性があるとみられています。
本間吏成アナ(小樽市 午後2時半)
「堺町通りもかなり雪解けすすんで、水たまりが多くなっています。観光客は歩きづらそうで、大きな水たまりを避けるようにして歩いていますね。」
全文・動画はこちら
https://news.yahoo.co.jp/articles/0bf4c563f9ff95bcb88df0aa0e8072daf3290108