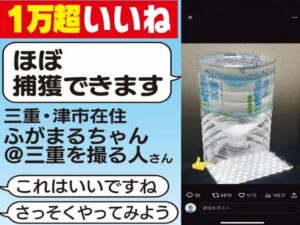大阪市天王寺区にある天王寺動物園で、獣医の男性がチンパンジーに噛まれ顔面にケガをし搬送されました。チンパンジー1頭が檻から逃げていて、現在、園内で捜索中だということです。
10月17日午前10時40分ごろ、天王寺動物園で40代の獣医の男性がチンパンジーに噛まれたと消防に通報がありました。男性は顔をケガするなどしていて、意識はあるということです。
警察などによりますと、チンパンジー1頭が檻から脱走したということです。職員らが園内で現在捜索中だということですが、園は客を退園させ、臨時休園の対応としました。
園内では退園を呼びかけるアナウンスが繰り返され、「落ち着いて職員の指示に従ってください」と呼びかけられていました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/0f0570c8e34c6051bb0dba4ef6e20f4471920a99