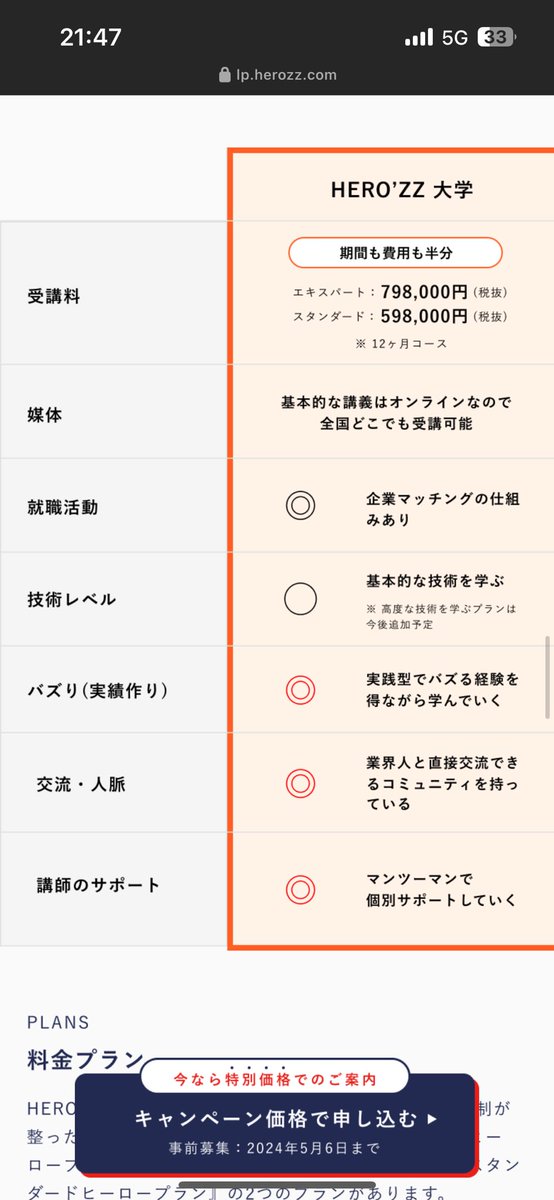「次の買い替えではEV(電気自動車)を選ばない」――。中国のEVオーナーの5人に1人が、購入したことを後悔しているという驚きの調査結果が明らかになった。
調査を実施したのはアメリカのコンサルティング大手、マッキンゼー・アンド・カンパニーの中国法人だ。同社は3月12日、「マッキンゼー中国自動車コンシューマー・インサイツ」と題する年次レポートの2024年版を発表。このレポートの2023年版では、次の買い替えでEVを選ばないとの回答はわずか3%だったが、2024年版ではそれが22%に跳ね上がった。
EVオーナーの不満の背景には、EVの急速な普及に充電インフラの整備が追いついていないことがある。
■地方都市では「後悔」が5割超え
マッキンゼーのレポートによれば、中国で「三級都市」「四級都市」と呼ばれる(充電インフラが脆弱な)地方都市では、EV購入を後悔しているオーナーの比率が54%に上った。一方、「一級都市」(北京市、上海市、広州市、深圳市の4大都市)や「二級都市」(省都クラスの大都市)では、同比率は10%にとどまった。
EV向け充電ステーションの業界団体のまとめによれば、中国全土の公共充電ステーションの設置箇所数で省・直轄市別のトップ10は広東省、浙江省、江蘇省、上海市、山東省、湖北省、北京市、安徽省、河南省、四川省の順だった。いずれも経済的に発展したエリアであり、充電インフラの地域格差が広がっている実態を示唆している。
マッキンゼーのレポートによれば、経済的に発展した北京市、天津市、上海市、広東省、浙江省、江蘇省の6省・直轄市では、EVの新規販売台数と公共充電装置の新規設置台数の比率が2020~2022年は7.1対1だったが、2023年には6.6対1に低下した。充電ステーションの建設が加速し、装置1台当たりのEVの数が減少した(充電しやすくなった)ことを意味する。
ところが、上記の6省・直轄市以外の地方では、同比率が2020~2022年の7.6対1から、2023年は9.1対1に上昇した。経済発展が(相対的に)遅れた地域では、充電インフラ不足でEVの使い勝手が悪化したのだ。
そんななか、中国の消費者の間では電池だけで走行する純EVより、ガソリンを給油すれば走り続けられるPHV(プラグインハイブリッド車)やレンジエクステンダー型EV(訳注:航続距離を延ばすための発電専用エンジンを搭載したEV)を評価する声が増えている。
■顧客のEV離れを防げるか
マッキンゼーのレポートによれば、PHVやレンジエクステンダー型EVの購入動機について、オーナーからは「長距離ドライブの際に電池切れを心配する必要がない」「通勤などの短距離移動ならEVモードだけで必要十分な航続距離がある」などの回答が多かったという。
また、EVは(中古車市場がまだ小さく)新車価格の高さの割に中古車としての評価額が低い傾向がある。このことも、EVオーナーの不満の高まりにつながっていると、レポートは分析している。
EVメーカーの立場では、充電インフラの整備を加速して利便性を高め、顧客のEV離れを防がなければならない。
例えば、レンジエクステンダー型EVを主力にしてきた新興メーカーの理想汽車(リ・オート)は、同社初の純EVの高級ミニバン「MEGA」を3月1日に発売した。それに先立ち、理想汽車は独自の急速充電ステーション網の建設を開始。2024年末までに中国全土に2万基の充電装置を設置する計画だ。
(財新記者:安麗敏)
https://news.yahoo.co.jp/articles/d9566a272b8b29f5c9d4dad2bac461b3516331d2?page=1
続きを読む