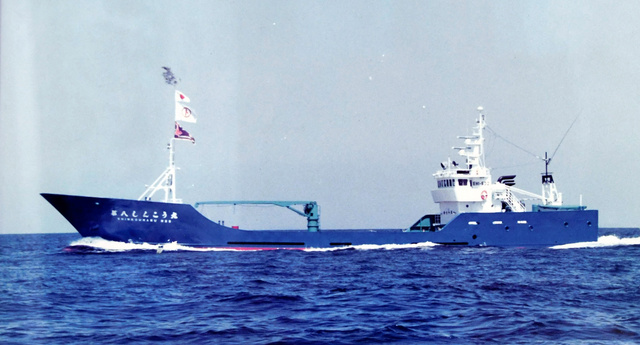2024年3月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国政府は全固体電池、リチウムメタル電池、リチウム硫黄電池など次世代バッテリー技術開発に今後5年間で1172億ウォン(約132億円)を支援することを決めた。2028年の開発を目標とする。
また、韓国のバッテリー企業3社(LGエナジーソリューション、サムスンSDI、SKオン)も今年、次世代バッテリー設備と研究開発に9兆ウォン以上を投入する計画だという。このうち設備への投資が7兆1000億ウォンに達すると伝えられている。
次世代バッテリーの中でも最も関心を集めているのが全固体電池だという。液体の電解質を固体にしたもので、エネルギー密度が高く火災のリスクは低い「夢のバッテリー」と呼ばれている。韓国政府は来月にも次世代バッテリー技術開発課題を発表し、下半期から本格的な事業に入るとしている。
全文はこちら
https://www.recordchina.co.jp/b930065-s39-c20-d0195.html